毎年4月1日から発売が始まる、京都人が愛するお菓子といえば[老松]の夏柑糖。夏みかんの中身を職人さんがひとつずつくり抜き、絞った果汁と寒天を合わせて冷やし固めた、おもたせに欠かせない春夏のお菓子です。いつまで店頭に並ぶかは、その年の収穫数によりけり。そんな自然に逆らわないお菓子作りを続け、便利さよりも豊かさを追求する、[老松]当主の太田達さんにその哲学を伺いました。

有職菓子御調進所 老松 当主、茶人、有斐斎弘道館 理事、立命館大学食マネジメント学部 教授、工学博士。専門は食文化、宴会論、伝統産業論など菓子文化研究意外にも多彩
食を軸にした観光をバスクで体感
取材の前日まで、フランスとスペインにまたがるバスク地方を訪れていたという太田さん。独自の文化を育むバスクで感じたのは、そこに生きる人たちがアイデンティティをしっかり持っている、ということだったそうです。
「食と観光が深く結びついていて、料理で博士号が取得できる大学(バスク・クリーナリー・センター)を有するバスクという都市にずっと関心がありまして。美食の街として知られ、スペイン側に位置するサン・セバスチャンにも立ち寄りました。ヨーロッパ屈指の観光地でありながら耳にするのはスペイン語でも、フランス語でもなく、バスク語。滞在中、スペインの国旗もひとつも目にしなかったと思います。そのぐらい自分の地域に愛着を持っているんです。サン・セバスチャンには小さなバルが100軒ほどあり、ワインを片手にピンチョスと呼ばれる一口サイズの料理をいただきます。名物ピンチョスを食べながら一杯飲んだら、隣の店へとどんどん移動、そら楽しいに決まってるでしょ。そうやってハシゴしているうちに、ピンチョスって懐石の八寸みたいやなって。京都でもお酒一杯と一品のセットで日本料理の店を何軒もハシゴできたら楽しいやろな、世界中の人が喜ぶやろな、なんて想像しながら巡っていました」。
楽しむという姿勢は太田さんの人生に欠かせないキーワードのようです。
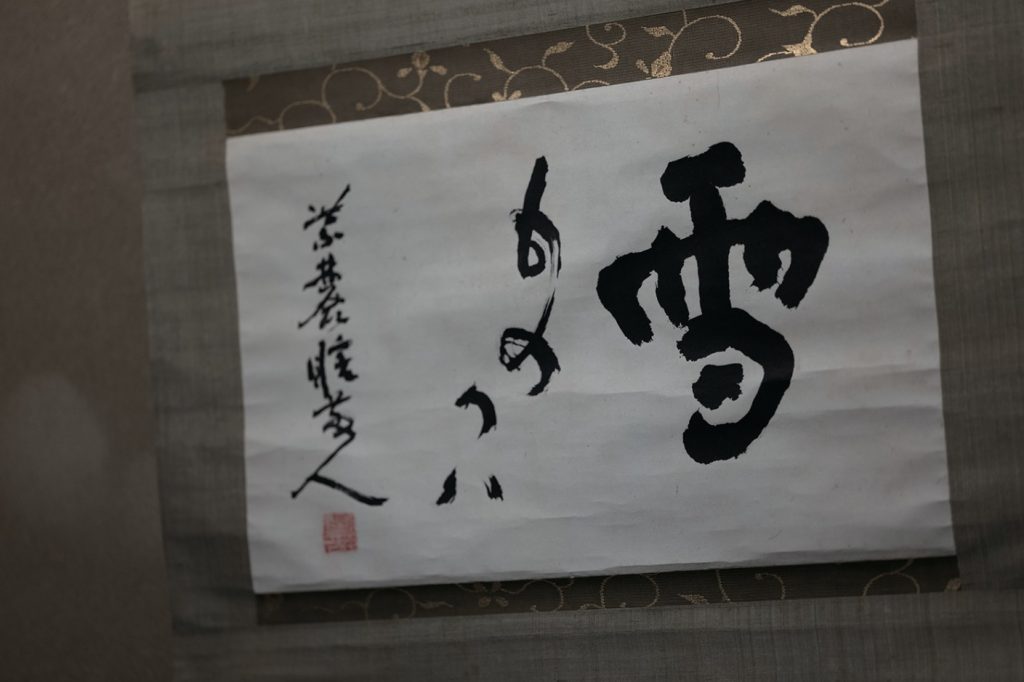

ビジネスに求めるボーダーライン
コロナ禍以前は、海外研修として社員の皆さんと毎年、未知なる土地を訪れていた太田さん。
「行き先はミャンマーの奥地とかボルネオ島とか、みんなが普段は行かないような、でも気になる国を選んで。ホテルはハイクオリティなところをリザーブ。到着した日だけみんなで一緒に過ごし、あとは最後の日までフリーにしてました。ハイクラスなホテルの対応方法、サービスに触れること、現地での味の記憶が僕らのビジネスに役に立つと思ったから。でもまあ、研修で学んでもらうというより、一緒に遊んでいたという感覚ですけどね。会社ではなく、和菓子文化を一緒に楽しむコミュニティです」。
会社の中に役職はなく、自身のことも代表や社長ではなく、「太田さん」と呼んでもらっているそう。そんなボーダーレスな経営者には、“ビジネスに求めるものは幸せ、決して金儲けではない”という明確なボーダーがあります。ここまでいけば従業員もお客様も幸せになれるというラインを見極め、売上の上限も決めているのだそうです。
「工房で働いてる子はもちろん、本店にいる子も、デパートの売り場に立ってる子も、社員約45人和菓子が作れて、職人はほぼ全員一級技能士です。作れて、経理できて、売り場に立てて、配達もできます。そんな有能な仲間である彼らが幸せで、楽しい人生を歩めれば、もうそれでいいわけです。便利は嫌いです、正直言って。だから、工房を機械化することも、面積を広げて効率化や量産化を図ろうと考えたことは一切ありません」。

「から衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思う」
の各句の頭文字をつなげたもの


もっとアイデンティティに 焦点をあてた京都観光が必要
スマートフォンを持っていないけれど、自分が調べたい情報は、どの図書館のどの棚にあるかわかり、車のカーナビは使わないけれど、世界中どこに行ってもタクシーの運転手ができるほど地図が読めるという太田さん。私たちは文明の利器によって生き方まで進化したように思っているけれど、実は便利になったことで失ったものの方が多いのかもしれません。第六感を鈍らせることなく新しい世界に飛び込んで、文化を革新していく太田さんの頭の中には、また新たな構想があるようです。
「例えば、お茶やお能など伝統文化が色濃く残る上京区あたりと、商業と工業で栄えてきた下京区あたりは、やはりアイデンティティが違う気がします。行政区分ができたのは、長い京都の歴史の中で、案外新しい。これまでのように京都をひとくくりに扱わず、もっとアイデンティティに寄ってコンテンツを掘り起こしてはどうか。そうする事でバスクのサン・セバスチャンのように、地域の誇りが輝き出す。地域にあるすばらしい文化を後世に残していくために、必要なことではないかと考えています」。
国境を越えて交わり、地域を大切にする。これからの観光のひとつのありかたを教わった気がします。



老松 北野店
☎075-463-3050
京都市上京区社家長屋町675-2
9:00〜17:00 不定休
P無
https://oimatu.co.jp/